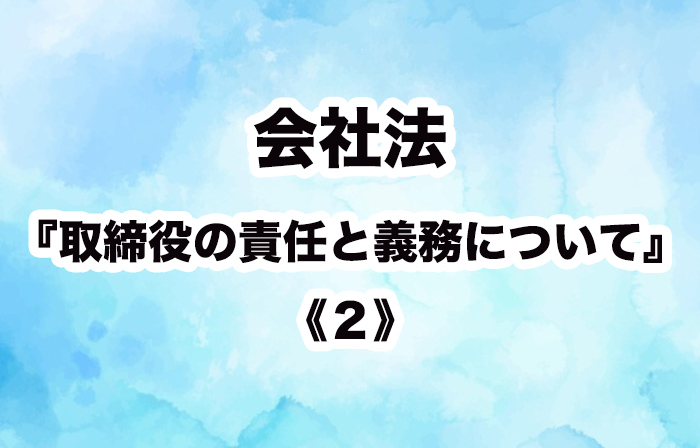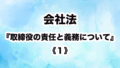前回に続き取締役はどんな責任・義務を負っているかみていきます。
前回は、1. 取締役の会社への責任について見ていきましたが、今回は2.取締役の第三者への責任と3.会社法第429条1項の各論点についてみていきます。
なお、判例が出てくる場合は裁判所名、年月日を記載していますので興味を持たれた場合は検索してみてください。
まずは前号の重要な点を確認しておきます。
それは、取締役は雇用契約ではなく委任契約だということです。
そのため、より細心の注意を払って職務を全うする必要があるということです。
では、続きに入っていきたいと思います。
2.取締役の第三者に対する責任
2-1 概要
会社法では、取締役の第三者に対する責任として429条1項を定めています。
本条文の具体的な内容は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」というものです。
この条文を適用する際に責任の本質についてどのような立場を採るかによって悪意・重過失の対象、不法行為責任との競合、損害の範囲、第三者の範囲に影響を及ぼすことになりますのでまずは責任の本質についてから説明していきます。
2-2 責任の本質の考え方
責任の本質の考え方としては、法定責任説(判例他)と不法行為特則説があります。
法定責任説とは、429条1項が一般不法行為法(民法709条)とは別に法が特に認めた法定責任であると解する考え方です。
これは、第三者が損害を受けた場合に、会社がその第三者に対して責任を負うのは当然ですが、それでは不十分な場合が少なくないことから、第三者の保護を厚くするために法定された責任であるとする考え方です。。
また、不法行為特則説とは、429条1項の責任は、一般不法行為の特則として、取締役の責任要件を悪意・重過失がある場合に限定したもの、という考え方です。
なお、判例や多くの学者は法定責任説の立場を採っているため、次項からは法定責任説の考え方を前提に置きつつ話を進めたいと思います。
2-3 責任の本質が及ぼす影響
2-3-1 悪意・重過失の対象
法定責任説によれば、悪意・重過失は任務懈怠(その任務を怠ったこと)、すなわち善管注意義務違反(民法644条)や忠実義務違反(会社法355条)について認められれば足りることになります。
したがって、一般不法行為法のように第三者に対する加害行為について悪意・重過失は必要ではないということです。
すなわち、相手に損害を与えることを意図していなくても委任に基づく受任者の注意義務(善管注意義務)や忠実義務を遵守していないことを知っていた場合や知っていないことについて重大な過失があった場合には429条1項の責任を負うということです。
また、役員等の任務懈怠に関し、会社法は423項1項において株式会社に対する損害賠償責任を規定しています。
任務懈怠責任の成立要件は、
① 任務懈怠があること
② 損害が発生したこと
③ 任務懈怠と損害の間に因果関係があること
④ 役員等に帰責事由があること
の4つがあります。
423条1項が争われた場合、①~③までは原告側が主張立証しますが、④の帰責事由に関しては役員等の被告側が主張立証しなければなりません。
これは、本来原告側が主張立証するものですが役員等に帰責事由があることを原告側が主張立証するのは困難であるため、主張立証する責任を被告側に転換したものです。
したがって役員等は自分に帰責事由がないことを主張立証できなければ423条1項の責任を負うということになります。
なお、ここでの帰責事由とは、故意・過失を意味し、履行補助者の過失も含みます。
すなわち、「すべての責任は役員等にあるから人に任せる時もしっかりチェックしろよ」ということを意味しているのです。
2-3-2 不法行為責任との競合
法定責任説によれば、429条1項の責任と民法上の不法行為責任は競合するため、第三者はいずれの責任を追及しても良いことになります。
2-3-3 損害の範囲
429条1項で賠償されるべき損害の範囲については3つの見解があります。
まず、直接損害に限定すべきとする見解です(直接損害限定説)。
直接損害とは、第三者が直接被った損害のことです。
次に、間接損害に限定する見解があります(間接損害限定説)。
間接損害とは、会社に第一次的な損害が生じ、その結果第三者が第二次的に被った損害をいいます。
最後は、直接損害と間接損害の双方を含むとする見解です(両損害包含説)。
この見解の論拠としては、直接損害と間接損害との区別が困難であることや、第三者の保護を強化すべきことが挙げられます。
法定責任説の立場からは3つの見解のいずれも取りうることができますが、判例は両損害包含説を採用しています。
なお、最高裁判所は昭和44年11月26日、大法廷において429条1項の責任を法定責任と解したうえで、賠償すべき損害の範囲について両損害包含説の見解に立つことを明らかにしています。
2-3-4 第三者の範囲
429条1項の第三者には会社債権者や直接損害を被った株主が含まれます。
これに対して、間接損害を被った株主については、429条1項の損害賠償責任を追及するのではなく、代表訴訟(会社法847条1項)によるべきであるとして、第三者に含まれないとする見解が有力です。
[東京高裁平成17年1月18日]
一方で、間接損害の意義を株価の下落による損害と定義するのか会社の受けた損害を持ち株比率で按分比例したものと定義するのかあいまいであること、株主代表訴訟は資格要件・担保提供等の点で訴訟提起のハードルが高いこと等から株主の間接損害についても損害賠償を認めるべきだとする見解があります。
3.429条1項の各論点
3-1 代表権のない取締役
代表取締役が取締役会決議を経ることなく独断で職務行為を行い、それにより第三者に損害が生じた場合、他の取締役は429条1項の責任を負うのでしょうか。
取締役会は代表取締役の選定及び解職をその職務の一つとしており(会社法362条2項3号)、また、代表取締役は取締役会が取締役の中から選定する(会社法362条3項)ことになっています。すなわち、代表取締役も取締役であり、取締役でない者が代表取締役を務めることはできないことになります。
そして、取締役会は取締役の職務の執行の監督を職務として定められています(会社法362条2項2号)。
そのため、取締役は取締役会の構成員たる地位に基づき、代表取締役の業務執行に対する監視義務を負うものと考えられます。
また、各取締役は取締役会の招集権を有している(会社法366条1項)ので、取締役会に上程されていない事項についても自ら取締役会を招集することで適切な業務執行が行われるように求めることができます。
よって、取締役の監視義務は、取締役会で議題に上った事項以外についても及ぶと解すことができます。
したがって結論としては、代表取締役の独断により第三者に損害が生じた場合でも、他の取締役が悪意・重過失により上記のような監視義務を怠った場合には429条1項の責任を負うということになります。
[最高裁判所昭和48年5月22日]
3-2 名目取締役
会社法の下では、取締役会は必要的機関ではありません。
ですが会社の信用力を高める目的で取締役会を設置し、その員数を確保するために、職務は負わない名目だけの取締役が就任する場合があり、このような名目取締役も429条1項の責任を負うかどうかが問題となります。
名目取締役であっても、選任決議を経て就任した以上、取締役であることには変わりがありません。
そして、名目取締役であることを理由として責任を負わないとすれば、取締役会設置会社において取締役の員数を法定し(会社法331条5項)、職務執行の適正化を図った法の趣旨が没却されます。
よって、名目取締役であっても業務執行に対する監視義務を負い、それを懈怠すれば429条1項の責任を負うことになります。
取締役会が設置されておりしっかりとした組織運営がなされていると信頼して取引を行った第三者からしてみれば、実は代表取締役だけが職務を執行し、代表取締役の独断で物事が決定されているとは思っていないであろうし、また、他の取締役が適切に監視義務を遂行していたかどうかを把握するのは容易ではありません。
そういった意味でも名目取締役は責任を負わないというのは第三者保護の観点からみてバランスを欠いていると考えられます。
[最高裁判所昭和55年3月18日]
3-3 表見取締役
登記簿上に取締役または代表取締役として登記しているが、株主総会における選任決議を経ていない者は、429条1項の責任を負うのでしょうか。
株主総会において選任されていない以上、登記があっても取締役としての権利義務を有さず、取締役とは言えないことから問題となります。
まず、429条1項は取締役の任務懈怠責任を規定するものであるから、取締役としての職務を有しない者は、同条の役員等には含まれません。
しかし、株主総会の選任決議は会社の内部事項であり、適法な選任決議を経たかどうかは第三者にとって容易に知りえないことが多いことから、第三者を保護する必要があります。
そのため、取締役就任登記に承諾を与えた者は、908条2項類推適用により自己が取締役でないことを善意の第三者に対抗できず、正規の取締役が任務懈怠とされる事態については同様の責任を負うと解されています。
それは、908条2項は禁反言をその趣旨とすると考えられ、取締役就任登記に承諾を与えることにより不実の登記作出に加功した者についても、同条を類推適用し得るからです。
[最高裁判所昭和47年6月15日]
3-4 退任登記未了の退任取締役
退任した取締役の退任登記がなされていない取締役は、429条1項の責任を負うのでしょうか。
登記が残っていても取締役とは言えないため問題となります。
すでに取締役を退任した者は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(会社法346条1項)。
しかし、そういった事情がない限り、429条1項に言う役員等には当たりません。
しかし、取締役としての登記が残存しているため、その者が取締役であると信頼した第三者を保護する必要があります。
そこで、本来退任登記がされているべき者が取締役として不実の登記がされていたものとして、908条2項を類推適用し、善意の第三者に対して自己が取締役でないことをもって対抗できない結果、429条1項の責任を免れないと解されています。
ですが、退任取締役は自ら退任登記をすることはできません。
そのため、退任取締役のあずかり知らないところで退任登記が未了となっており退任取締役の帰責性がないにもかかわらず退任取締役に429条1項の責任を負わせるのは酷だと考えられます。
したがって、908条2項の類推適用が認められるのは、その者が不実の登記を残存させることについて明示的に承諾していた等の特段の事情が必要になると考えられます。
[最高裁判所昭和62年4月16日]
3-5 事実上の取締役
上記で上げたほかにも事実上の取締役という問題があります。
事実上の取締役とは、株主総会における就任決議を経ておらず、かつ就任の登記もない者が、実際に取締役としての職務を執行していた場合に、429条1項の責任を負わせることができるかどうかという問題です。
この場合には、ある者が事実上取締役としての職務を執行している場合には、この者が行った対内的・対外的業務執行行為は原則として有効とされ、この者には法律上の取締役と同様の義務と責任が課せられると解されています。
いかなる場合に事実上の取締役といえるかについては十分な議論がなされているとは言えませんが、その一例として、①取締役としての外観と、②取締役の職務の継続的執行という2つの要件を満たす場合が挙げられています。
4 おわりに
前回と今回とで会社法において取締役の責任がどのように規定されているのかを見ていきました。
この原稿の執筆にあたっては私も会社法の専門書を読み、勉強し直しました。
そこで感じたことは法律を少なからず知っておくということは自分の身を守るために必要なことだということです。
今日の経済社会において会社(特に株式会社)の存在はとても大きくこれなしでは成り立ちません。
そのため、株式会社の代表(顔)である取締役が不正や不祥事を起こしたとなると世間からの信頼がなくなり延いては社会そのものが成り立たなくなります。
こういったことを防止するため会社法においては取締役の責任を重くしているのです。
取締役の方々には自分たちがどういった責任を負っていてどのような行動を心掛けなければならないかをしっかりと理解してもらう必要があります。
そのため、取締役の方々も常に勉強が必要となってきます。
法律の勉強は条文に書かれていることだけでは足りません。
法律や条文が設けられている趣旨を考えて条文に記載がないことであっても結論を出す必要があります。
判例を勉強する意味はここにあります。
詳しいことは弁護士に聞けばよいのですがビジネスをしようとするときに毎回弁護士に聞いてから答えを出すようではスピーディーさに欠けビジネス機会を逃してしまいます。
特に新しいことを始めようとするときはしようとしていることが法律違反となるかどうかわからないことも多くあります。
ですが新しい技術を開発したりするなどよっぽど新しいこと(まだまだ法整備が追いついていないようなビジネス)をする場面以外では判例が形成されているものも多くあると思いますので現在自分たちが行っているビジネスに関連するような判例を調べてみるだけでもかなりの効果があると思います。
本文で紹介した判例は法律を勉強するうえで重要なものであり、同じようなことを争って行われる裁判は数多くあります。
そのため、調べてみたら自分たちが置かれている状況とほぼ同じような状況に置かれている人が裁判しているということもあり得ます。
そういった判例を調べてみて自分の身をどう守っていけばよいのかを勉強することでよりスピーディーにかつ自信を持ってビジネスを行うことができると思います。
なお、本文中に判例の情報を載せましたが詳しくご覧になりたい方はネットで判例を検索できるサイトもありますのでそちらでご確認ください。
裁判所がどういったロジックで最終的にどういった結論を出しているのかを読むことができるので是非調べてみてもらいたいと思います。
今回の執筆にあたっては『会社法の基礎 加藤徹・伊勢田通仁(2019年3月30日 法律文化社)』を参考にしました。
最後に、何か法的に、困ったことがあれば、日新税理士事務所と提携している弁護士さんを紹介させて頂きますのでご一報くださいませ。
(千日 瑞生)