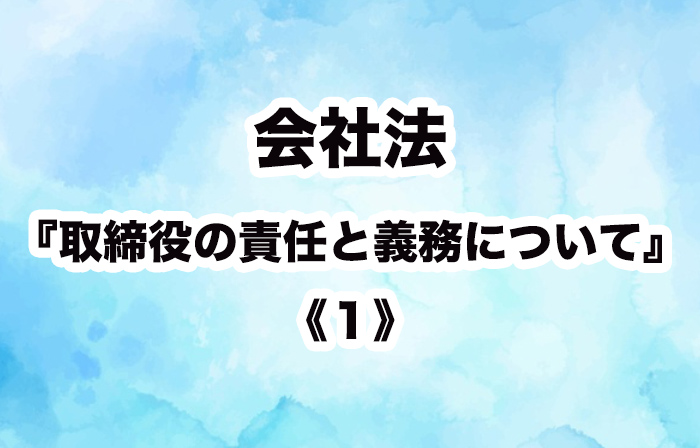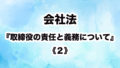取締役はどんな責任・義務を負っているのでしょうか。
今回は1. 取締役の会社への責任2. 取締役の第三者への責任について見ていきたいと思います。
なお、判例が出てくる場合は裁判所名、年月日を記載していますので興味を持たれた場合は検索してみてください。
まず、個別の論点に入っていく前に取締役の立場を理解しておく必要があります。
会社法330条では、取締役は株式会社との関係で委任に関する規定に従うとされています。
株式会社(株主)が委任者、取締役が受任者という関係になります。委任契約に関しては会社法ではなく民法643条に規定されています。
ここで重要な点は雇用契約ではないということです。
そして民法644条では受任者の注意義務が規定されています。
これは、俗に善管注意義務と呼ばれているものです。
善管注意義務とは、善良な管理者の注意義務の略であり、自己の所有物を管理する際に払う注意よりも細心の注意を払うことを要求するものです。
そして会社法355条では忠実義務を規定していますが、これは、善管注意義務とは全く違ったものというわけではなく、民法に規定している善管注意義務をより意識づけるために会社法において一層明確にしたものであると判例や多数説(多くの学者が採用している考え方)では解釈されています。
そして、取締役がこの善管注意義務や忠実義務に反した場合には任務を怠ったということで任務懈怠責任(会社法423条1項)を負うことになります。
[最高裁判所昭和45年6月24日]
さらに、会社法では忠実義務のような抽象的な義務の他に、個別的な規定を置いて、取締役が会社の利益を害することを防止しています。
1.取締役の会社への責任
1-1 競業避止義務
取締役の会社に対する義務の個別的規定の一つとして競業避止義務が挙げられます。
これは、取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとする規定です(会社法356条1項1号)。
取締役は会社の業務執行について強大な権限を持っており、機密事項に触れる機会も多分にあります。
また、前述のように取締役と会社には委任に基づく関係があります。
そのような状況で取締役が自由に会社と同類の事業を営むことができるとすれば、会社に大きな損害をもたらすことになります。
そのため、会社法は株主総会への報告と承認が必要であると規定しているのです。
では、具体的にどういった場合に問題になるのでしょうか。
まず、356条1項1号には「自己又は第三者のために」と規定していますがその意義と判断の基準が問題になります。
重要な点は、会社の損害を防止するためにこの規定があるということです。
したがって、経済的効果の帰属が誰になるのかによって判断されます。
そのため、取締役が個人の名義で取引をしたとしてもその利益が会社に帰属するのであればこれを規制する必要はありません。
よって、取締役の名義で行ったか、会社の名義で行ったかという形式的な判断ではなく取締役や第三者に利益が帰属するかという実質的な判断で本条文は適用されるということです。
続いて、「会社の事業の部類に属する取引」の意義についてです。
事業の部類とは、会社のノウハウや対象としている顧客と競合するような事業を行うことを指します。
では、具体的に取締役が競業を図った結果、会社が受ける損害としてはどのようなものがあるでしょうか。
技術情報や製品情報、重要な顧客情報やそれをもとに分析したデータ情報が奪われることになります。
その結果、その後何年にもわたって利益が侵食されることにつながります。
さらに悪質になれば同じような新製品の情報などを先に公開し顧客を奪ったうえで投資家等に対して将来性についての不安を覚えさせ、株価を操作するということも考えられます。
356条1項1号の趣旨はこのような具体的な損害を与えることを禁止する点にあります。
また、競業の範囲には、定款所定の目的である事業でも完全に廃業している事業は含まれません。
一方で、一時的に休止している事業や開業準備に着手している事業は含まれます。
判例では、取締役が、全く異なる遠隔の地域で事業を始めた場合でも、会社がその地域へ進出する準備行為を行っている場合は競業避止義務に反するとしています。
[東京地方裁判所昭和56年3月26日]
競業避止義務違反があった場合でも、取引は相手方の善意・悪意を問わず有効となります。
なお、法律上で用いられる善意・悪意とはある事実について知らないことを善意、知っていることを悪意といいます。
つまり、日常会話で使われる悪意のようにその言葉に感情が入っているようなものではありません。
また、法律学では、『法の不知はこれを許さず』という言葉があります。
これを表したのが刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」です。
つまり、法律には、ある事実に関して善意の者に対して助け舟を出すことはあっても法律自体を知らない(善意)者に救済措置は講じないということです。
損をしたくなかったら法律を勉強しろということです。
話を戻し、なぜ相手方が競業避止義務違反であることを知っている(悪意である)取引においても有効となるのでしょうか。
例えば、取締役Xが相手方Yに商品を売ったとします。
そして相手方Yは取締役Xから仕入れた商品を第三者に売ったとします。
このような場合に取締役Xと相手方Yとの取引が無効だとすると相手方Yと取引をした第三者は不安定な立場に置かれることになり、安心して取引をすることができなくなります。
また、会社が被った損害は取締役が得た利益の額と等しいと推定される(会社法423条2項・1項)ため、会社は取締役に損害賠償請求をすれば足り、取引を無効にする必要はないと考えられるからです。
また、会社に損害が生じた場合は、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認の有無にかかわらず、取締役は会社に対して損害賠償義務を負います(会社法423条1項)。
ただし、取締役は、自らの任務懈怠が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを立証できれば、423条の定める損害賠償義務を免れることができます。
以上が取締役の競業避止義務に関しての内容です。
取締役は責任のある立場のため非常に重たい規制がかけられています。
したがって、取締役に就任する者は、「会社は自分のものではなく、会社を最優先に考えて行動しなければならない」という考えをもって仕事をしなければなりません。
また、取締役は相互に監視義務を負っているので他の取締役に会社の損害をもたらすような怪しい行動がないかどうかも注意する必要があります。
1-2 利益相反取引
競業避止義務の他にも個別的規定が設けられています。
それが利益相反取引の規制です。
利益相反取引とは、取締役と会社の利害が対立するような取引のことを言います。
具体的に利益相反取引には、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」(会社法356条1項2号)と、「株式会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」(会社法356条1項3号)があります。
3号の前半部分は、会社が取締役の借金を肩代わりすることです。
後半部分は第三者を経由して行われるような取引です。
このような場合には競業取引の場合と同様に株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認が必要とされます。
会社法356条1項2号でも「自己又は第三者のために」という文言が出てきますが、利益相反取引における「自己又は第三者のために」とは、自己又は第三者の名義でという意味であると解されています。
これは競業取引とは異なり、間接取引(会社法356条1項3号)が明文で規制されているため、このように解しても会社に対する損害を阻止するという356条の趣旨に反しないからです。
そして、356条1項3号で規制の対象となる取引は外形的・客観的に会社の犠牲で取締役に利益が生じる形の行為です。
したがって、取締役が会社の債務を保証する場合は会社の利益となるため規制の対象になりません。
また、競業取引の場合には自己の責めに帰することができない事由によるものであることを立証できれば損害賠償義務を負わないと前述しましたが、利益相反取引では、自己のために直接取引(会社法356条1項2号)を行った場合は、自己の責めに帰することができない事由によるものであったとしても損害賠償責任を負うことになります(会社法428条1項)。
利益相反取引の話を読んでカルロス・ゴーン氏の逮捕を思い浮かべる方も多いと思います。
ゴーン氏は自身の損失を日産自動車に負担させた疑いがあるとして逮捕されました。
容疑は特別背任罪です。
これは刑法247条で規定されている背任罪の特別法として規定され、より重い罪が科せられます。
会社法では960条において特別背任の規定が設けられています。
具体的には、「(前略)十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」ととても重い罰則が定められています。
また、未遂についても罰せられることが規定されている(会社法962条)ため、実際には行わず計画しただけであっても罪に問われます。
したがって、競業取引のところでも前述しましたが、取締役等には非常に重たい責任が課せられているので、常にそのことを自覚して行動することが求められます。
1-3 取締役の報酬等
会社法では取締役の報酬に関しても規制を設けています。
自分たちの給料を自分たちで決めるということは不正が起こりやすいからです。
ここで問題となるのが使用人兼務取締役の報酬です。
判例では、代表権を有しない取締役は、同時に支配人、部長などの使用人を兼務し得るとしています。
このような使用人兼務取締役に支給される使用人としての給与は、361条1項の報酬等にあたるかが問題となります。
[最高裁判所昭和60年3月26日]
取締役の報酬に関しては、報酬の具体的な額や計算方法を定款に定めておくか又は株主総会の決議によって定めるものとされています(会社法361条1項1号、2号)。
まず、361条1項で規定している報酬等は取締役の職務執行に対する対価であり、使用人としての給与はこれには含まれません。
しかし、そのように解すると、取締役分と使用人分の報酬を操作することで361条1項が潜脱され得ることになります。
そこで、株主総会で取締役としての報酬を決定する際に、使用人としての給与を別に支給する旨を明らかにすることを要し、これを明らかにしなければ使用人としての給与を支給できないと解します。
また、判例では、使用人兼務取締役が取締役として受ける報酬額の決定についても、少なくとも使用人給与の体系が明確に確立されており、かつ使用人給与がそれによって支給されている限り問題ないとしています。
また、使用人給与の体系が明確に確立されている場合であれば、使用人兼務取締役について、別に使用人給与を受けることを予定しつつ、取締役の報酬額のみを株主総会で決議するとしても株主総会が監視機能を十分に果たせなくなるとは考えられないとしています。
1-4 おわりに
今回は取締役の会社への責任について見ていきました。
次回は、第三者への責任について見ていきたいと思います。
なお、本文中に判例の情報を載せましたが詳しくご覧になりたい方はネットで判例を検索できるサイトもありますのでそちらでご確認ください。
今回の執筆にあたっては『会社法の基礎 加藤徹・伊勢田通仁(2019年3月30日 法律文化社)』を参考にしました。
最後に、何か法的に、困ったことがあれば、日新税理士事務所と提携している弁護士さんを紹介させて頂きますのでご一報くださいませ。
(千日 瑞生)