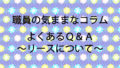はじめに
世の中には、自然に生じるパターンというものがある。
周囲の人を感激させ、奮起させる力、すなわち人をインスパイアする能力をもつリーダーたちのものの考え方、行動様式、コミュニケーション術もまたそうしたパターンのひとつだ。アップルコンピュータは、庶民ひとりひとりの手にパソコンをゆきわたらせることができれば、圧倒的に豊かな資源に恵まれた企業と同じような機能を個人がはたせるようになる。
パソコンがあれば、個人と組織が同じ土俵で勝負できるようになる。
そしていずれは世界の仕組みを変えるだろう。アップルは固定観念に挑戦し、成功した。
その理由はいたってシンプル。アップルは人々を鼓舞(インスパイア)するから。
アップルはWHYから始めるからだ。
インスパイアできるリーダーは、誘惑や脅迫といった手段を使わずに、人に目的意識や帰属意識をもたせる。
真の意味でのリーダーがいれば、人は短期の利益を上げたいからではなく、感激して勇樹をもらったからこそ行動を起こす。
人をインスパイアすることができるリーダーには賛同者――支援者、投票者、顧客、労働者――がつく。
上の人間から強制されたからではなく、みずからの意志で、全体のために行動を起こす。
第1部 WHYから始まらない世界
勝手な思い込みや、真実と思い込んだ考え方に影響を受け、私たちは行動を起こすからだ。
私たちは、自分が知っていると思っているものを基盤に判断をくだす。
「どうして貴社の顧客は忠実にずっと顧客でありつづけているのでしょう?」と尋ねれば、大半の企業は「品質・特色・価格・サービスのどれをとっても当社の商品のほうが優れているからですよ」と応じるだろう。
言いかえれば、なぜ自社の顧客が顧客でありつづけているのかが、大半の企業にはまるでわかっていない。
人間の行動に影響を及ぼす方法は、ふたつしかない。操作(マニピュレイト)するか、鼓舞(インスパイア)するか、だ。
自社の顧客がずっと顧客でありつづけている理由を明確に把握していない場合、企業は望みのものを手にいれようとむやみやたらに操作をおこなう。
操作にすっかり依存してしまうのだ。
無理もない。
操作には効果があるのだから。
価格競争に参入すると莫大なコストがかかり、会社にとって大きなディレンマとなる。
売り手にしてみれば、安値を基盤に商売をするのは麻薬に手をだすようなものだ。
平均よりも安い価格で製品やサービスを購入することに一度慣れてしまった買い手にたいして、こんどは平均以上の価格で商品を買ってくださいと頼むのはむずかしい。
いまや消費財のほとんどがコモディティ化しており、価格競争に参加している商品のリストをつくれば、きりがない。
ほぼすべての分野において、企業は自社製品をコモディティとして扱わざるをえなくなっている。
「一個の価格でいまなら二個」、「付録でオモチャがついてくる」など、プロモーションはいまなおごくあたりまえにおこなわれており、私たちは自分が操作されていることをつい忘れてします。
実際に身に危険が迫っていようが、そう思い込んだだけであろうが、恐怖心の利用は大衆を思いどおりに動かすうえでもっとも有効な操作といえる。
恐怖心が作用すると、事実は二の次になる。
なんとしても生き延びたいという本能は生物学的に私たちのなかに深く根づいており、いくらデータや事実を目の前にしても簡単に消し去ることはできない。
その商品を購入しなかった場合、おそろしいことが起こると脅してなにかを売りつけるのは、競合他社ではなく弊社の商品を選ぶ「価値」について銃をつきつけながら説明しているようなものだ。
いや、それは銃ではなく、ただのバナナかもしれない。
それでも、効果はある。
「大半の人が(あるいは専門家の一団が)よその製品より自社の製品を好んでいます」という宣伝は「なにを売っているのかよく知らないが、その製品はきっといいに違いない」と消費者に思い込ませようとしている。
消費者が不安を覚えるからこそ、仲間集団からのプレッシャーは作用する。こうしたプレッシャーにくわえ、よく利用されるのが有名人の推薦の弁だ。「あの人が使っているのなら、いい製品に違いない」と思わせるのだ。
本物のイノベーションとは、産業の歩みを変える、あるいは社会の歩みさえも変える。
電球、電子レンジ、ファクシミリ機、iTunes。
これらは本物の革新であり、ビジネスの形態や私たちの生活様式を変えた。
だが、携帯電話機にカメラの機能をくわえた技術はイノベーションではない。
――たしかに大きな特色ではあるが、ひとつの産業界を変えるほどのものではない。
たくさんの特色をくわえて差異化をはかろうとすればするほど、その製品は他社の製品と差異がなくなる。
他社製品と差異がなくなったからと、また新たな特長をつけくわえようとすると、結局は負のスパイラルから抜けだせなくなる。
第2部 WHYから始まる世界
人を操作するのではなく、人を感激させてやる気を起させる、つまりインスパイアできるリーダーは少ない。
それが個人であれ、組織であれ、人をインスパイアするリーダーはまったく同じ方法で行動し、コミュニケーションをとっている。
予測不可能なものの象徴であった母なる自然にさえ、いまでは、さまざまな理法があることがわかっている。
〈ゴールデン・サークル〉は、人間の行動には予測可能なものがあり、そこには理法があることを教えている。
〈ゴールデン・サークル〉は、最初に「なぜ」と自分することですべてを始めようと肝に銘じていれば、以前よりずっと大きなことを達成できるという動かしがたい証拠を示している。
〈ゴールデン・サークル〉は、世界を変える役に立つだけではない。
これを応用すれば、人にやる気を起させる能力も身につく。
リーダーシップ、企業文化、雇用、製品開発、営業、マーケティングを飛躍的に改善することもできる。
忠誠心の本質もわかるようになるし、ひとつのアイディアを社会運動へと変える推進力の起こし方もわかるようになる。
〈ゴールデン・サークル〉は、円の中心から始まる。
すべてがWHY(なぜ)から始まるのだ。円の外側から内側へと、順に説明していく。
WHAT:企業や組織は、自分のWHAT(していること)がわかっている。
自社が扱っている製品やサービスのことならだれだってすらすらと説明できるし、会社や組織のなかで自分がどんな職務についているかも簡潔に説明できるはずだ。
HOW:自分がしていることのHOW(手法)を知っている人や企業も、なかにはある。
「価値観に差異をもたせる」、「独自の工程」、「ユニークな販売計画」など、よそとは違う方法、よりよい方法をとるのだ。
これをHOWと呼ぶ。
HOWはたいてい、WHATほど明確ではない。
WHY:自分がいましていることを、しているWHY(理由)。これを明言できる人や企業は少ない。
このWHYには「お金を稼ぐため」という理由は含まれない。
私がWHYと問うとき、それは、あなたの目的はなんですか、大義や理念はなんですかと尋ねているのだ。
傑出した企業は違う。
傑出したリーダーも違う。
かれらは、内側から外側へと向かう順に考え、行動し、コミュニケーションをはかっている。
人々は、あなたのWHATを買うわけではない。
あなたがそれをしているWHYを買う。
組織はよく、他社の製品やアイディアより自社の製品やアイディアのほうが優れている理由を合理的に論じるころで、製品に具体的な特色をもたせ、利益を上げようとする。
しかし、円の内側から外側へとコミュニケーションをはかると、消費者が買い物をする理由がWHYとなり、社の信条を具体的に立証したものがWHATとなる。
そうなったとき初めて、ある製品、ある会社、あるアイディアに惹かれる理由を、消費者はきちんと説明できるようになる。
WHATとそれをしているWHYのあいだに明確な相互関係があるからこそ、アップルは傑出した存在となっている。
アップルがしていることはどれをとっても、かれらのWHY、つまり、「現状への挑戦」の実演である。
どんな製品をつくろうが、どんな産業に参入しようが、アップルの「シンク・ディファレント」(異なる考え方をしろ)はつねに明確だ。
ある企業のリーダーが、製品やサービスといった言葉を使わずに自社の存在意義を明確に説明できないなら、毎日、自分がなんのために出社しているのか、従業員にわかるはずがない。
争点となっているたったひとつの論点などより、もっとおおきなことについて信頼できる人物でないと、リーダーにはなれない。
人をインスパイアしたければ、まず、志や理念といった自分のWHYを明確にしておこう。
あなたがしていることを、なぜしているのですか?
――は、じつにシンプルであり、効率よく答えを見つけることができる。
指針を明確にするには、動詞を使うといい。
「誠実」ではなく、「つねに正しいことをしよう」と書こう。
「イノベーション」ではなく、「問題を違う角度から眺めよう」と書こう。
自分の価値観を動詞で表現すると、はっきりとしたアイディアが浮かび、どんな状況に直面しても、どう行動すべきかが明確にわかるようになる。
WHYは、ただの信条である。
HOWは、その信条を理解するために起こす行動だ。
WHATは、そうした行動の結果である。
第3部 リーダーには信奉者が必要
20年間、サウスウエスト航空のトップを務めたハーブ・ケレハーは、まず従業員を大切にしなければならない、それが企業の責任だと断言し、異教徒と見なされた。
彼に言わせれば、従業員が幸せになれば、客もまた幸せになる。
そして客が幸せなれば、株主もまた幸せになる――それが順番なのだ。
勝ちたいという欲望は、本質的に悪いものではない。
ところが得点だけが成功の基準になると、問題が生じる。
そもそも、最初に動機としていたはずの自分のWHYを忘れ、得点稼ぎだけに夢中になってしまうからだ。
成功を続けるためには、従業員が自分のために勝ちたいと思わねばならない。
文化を形成する能力があったからこそ、人類は種として成功をおさめた。
文化とは、同じ価値観や信条をもつ人々の集合体だ。
ほかの人の価値観や信条を共有できれば、そこから信頼が生まれる。
自分と同じものの見方をする人、理念や信念を分かちあえる人と友人になる。
企業は文化である。
だからこそ、従業員を雇う際には、必要な技術や能力があるからではなく、自社の理念に心から共感を覚える人材を見つけなくてはならない。
大いなる企業は、技術力のある人を雇い、かれらにやる気を起させるような真似はしない。
やる気満々の人を雇い、かれらをインスパイアする。
人間は、やる気がある人とない人に分けられる。
信じられるものを示し、仕事それ自体よりもっとおおきなものをめざして働こうという意欲をもたせることができなければ、従業員は転職に意欲を燃やすようになるかもしれない。
WHYの意識をもつという、ただそれだけで、仕事全体の見方が変わるのだ。
当然、生産性も上がるし、忠誠心も生まれるだろう。
似たような考え方をする人々を集め、かれらに理念や大志をもたせると、チームワークや同志愛という大きな意識が生まれる。
リーダーの役割は、さまざまな名案を示すことではない。
リーダーの役割は、名案が浮かぶような環境と整えることだ。
WHYを明確にもっている社員は、ちょっと失敗したくらいではへこたれない。
自分にはもっと高い目標があることがわかっているからだ。
トーマス・エジソンはこう語っている。
「私は電球をつくるひとつの方法を見つけたわけじゃない。電球をつくれない1000もの方法を見つけたのだ。」と。
サウスウエスト航空おたぐいまれなる問題解決能力、アップルのすばらしいイノベーションの技術、手持ちの人材で新たなテクノロジーを生み出したライト兄弟の能力には共通点がある。
「自分たちにはできる」、「仲間たちがやってくれる」と信じていたことだ。
第4部 信じる人間をどう集結させるか
大きな成果を上げたカリスマ性のある偉大なリーダーのそばには必ず、リーダーのビジョンを理解し、それを現実のものにするHOWを知る個人やグループが影のように存在する。
WHYタイプは夢想家であり、あまりにも活発な想像力の持ち主だ。
だから楽観的になりがちで、想像したことはすべて実現可能だと考えてしまう。
いっぽうHOWタイプは、もっと現実を生きている。
かれらは現実主義者であり、実務的なことがらに鋭敏だ。
WHYタイプは、大半の人の目には見えないものを見ようとし、未来を見すえようとし、構造や組織をつくりあげ、きちんとしたプロセスを経て、目標を達成するのが得意だ。
HOWタイプは、ものごとをきちんとおこなうためにWHYタイプを必要とはしない。
実際のところ、成功した起業家の大半はHOWタイプだ。
最高のHOWタイプは、前面に立ってビジョンを説こうとは思わず、陰に身を置き、ビジョンを実現するシステムを構築しようとする。
その際、技術と努力が合体しないかぎり、偉大なる成果を上げることはできない。
組織は〈ゴールデン・サークル〉の三次元の円錐形の図によってあらわされる。
この組織化されたシステムは、もうひとつのシステムの上に載っている。
そのシステムとは、市場だ。
市場は、顧客、顧客になる可能性のある人、マスコミ、株主、ライバル社、サプライヤー、カネでなりたっている。
このシステムはもともと混沌としており、秩序がない。
その上部にある組織化されたシステムとの唯一の接点は、円錐のいちばん下にある秩序のない部分――WHATのレベルである。
組織の言動はすべて、外の世界に向けてリーダーのビジョンを伝える役割をはたす。
小規模な会社は、創業者の個性を中心に回転する。
会社が成長するにつれ、CEOの仕事はWHYの化身になることになる。
全身から信念がにじみだすようにし、理念について語り、大義を諭す。
会社が信じているもののシンボルになるのだ。
リーダーの仕事は詳細を詰めることではない。
人々を感動させ、鼓舞することなのだ。
組織が成長するにつれ、リーダーは会社がしているWHATから物理的にどんどん遠ざかる。
円錐形が示すようにCEOの仕事は、つまりリーダーの仕事は、つまりリーダーの責任は市場の外に集中することではない。
そうではなく、その真下にある層に集中することだ。
すなわちHOWに目を向けるのだ。
リーダーは、メンバーに信念を確実に信じさせ、それを実行する方法を確実に理解させなければならない。
第5部 成功は最大の難関なり
サム・ウォルトンにはもっと大きな目的、理念、信条があったからこそ、仕事に邁進した。
なによりも、ウォルトンは人間を信じていた。
人の世話をすれば、相手もまた自分の世話をしてくれると信じていた。
ウォルマートが従業員、顧客、地域に多くを与えれば与えるほど、従業員、顧客、地域がより多くのものをウォルマートに返してくれるはずだ、と。
「われわれはみな、一丸となって働いている。それが秘訣だ」と、ウォルトンは言った。
ウォルトンにとって、着想は顧客サービスから生まれるのではなく、サービスそれ自体から生まれるものだった。
ウォルトンにとってウォルマートは、自分の同志である人類に貢献するためにつくりあげたWHATだった。
地域に、従業員に、顧客に貢献する。
彼にとってサービスは、非常に崇高な使命を帯びていた。
「成功したら、祝いなさい」と、ウォルトンは言った。
「失敗したら、少しでもユーモアを見つけなさい。
あまり深刻に考えこまないことだ。
あなたがリラックスすれば、周囲に人もリラックスする」。
起業したあと、あるいは仕事を始めたあと、自分がおこなうWHATに私たちは自信を深めていく。
そして、それをおこなうHOWに精通していく。
業績を上げれば、どれだけの成功をおさめたかを具体的な数値で知ることができ、これでまた精通した、成功したと感じることができる。
人生はいいものだ。
ところがその過程で、そもそもどうしてこの旅を始めたのかというWHYをすっかり忘れてしまう。
すると、必ずWHATとWHY乖離が生じる。
これは組織の場合も個人の場合も同様だ。
最初のうち、アイディアには情熱というエネルギーが注がれる。
ところが、多くのスモールビジネスが失敗するのは、情熱だけでは足りないからだ。
情熱を持続させるためには構造が必要となる。
構造なき情熱、つまりHOWなしのWHYでは、失敗する確率が高い。
みなさんはドットコム・ブームを覚えておいでだろうか?
シリコンバレーを中心にベンチャー企業が次々と誕生したあの時代、あふれんばかりの情熱はあったものの、しっかりとした構造がともなっていなかった。
ウォルマートと同様、エンディコット・ハウスに集まった起業家たちもかつては、〈ゴールデン・サークル〉の内側から外側へと向かう――WHYからWHATへの――順番でものごとを考え、行動し、コミュニケーションをはかっていた。
だが成功するにつれ、その順序が逆になりはじめた。
最初にWHATを、つまり具体的な成果を上げるためのシステムやプロセスをいちばん最初に考えるようになったのだ。
こうした変化が起こった理由は簡単だ――WHATとWHYが乖離し、WHYが曖昧になったのである。
どんな組織でも直面する、唯一かつ最大の難関は――成功だ。
会社の規模が小さいあいだは、創業者は自分の直感を頼りに大きな決断をくだす。
ところが組織が大きくなり、いっそう大きな成功をおさめるようになると、すべての重要な決断をひとりの人間がくだすのは物理的に不可能になる。
すると他人を信頼し、大きな決断をくだしてもらうだけでなく、だれを雇用するかも決めてもらう必要がでてくる。
そうしてメガホンが大きくなるにつれ、ゆっくりと、だが確実に、WHYの明晰さは薄れていく。
リーダーにしがみつくのではなく、創業の精神を永遠に伝えていく効果的な方法を見つけなければならない。
創業者のWHYが企業文化に浸透し、融合しなければならない。
どうしても達成したいと思える目的や大義や信条がなければ、会社などスタッフの集まりにすぎない。
じきにばらばらになり、スクラップとして売られてしまう。
成功をおさめた起業家が、初期に必ずなにかを切望していたのは、偶然ではない。
多くの大企業が「初心に戻れ」と異口同音に言っているのも、偶然ではない。
かれらがほのめかしているのは、乖離が始まるまえの時代に戻れということだ。
自分のWHATとWHYと完全に一致していた頃に。WHYを犠牲にし、WHATの成長だけに集中してこのまま進んでいけば、容量ばかりが増え、明晰だった理念は薄れてしまう。
人々をインスパイアし、成功をおさめることもできなくなる。
WHYを明確にしておこうと数値化するのはむずかしい。
債権回収代行会社の女性社長であるハーブリッジは、たとえ、電話をかける目的が借金の取立てであろうとも、会社がおこなっているWHATではなく、会社が存在するWHYを礼状の数という数値であらわした。
その結果、思いやりがなによりも尊重される文化がうまれたのである。
だが、ほかの結果は?業績は?業界平均の300%に相当する金額を回収した。
それだけではない。
当初は回収の対象だった個人や会社が、回収を依頼してきた企業、つまりかれらが借金をしていた企業と、いっそう取引をするようになった。
これは回収代行業界では前例のないことだった。
ビル・ゲイツでされ、リーダー不在のときに拠り所にできるよう、理念をはっきりと言葉で伝えることができなかった。
自分たちの活動を具体的な言葉で示すことができなければ、次世代のリーダーをつくることはできない。
企業の文化は、ひとりの人間のビジョンを基盤に築きあげられている。
だからこそ、後継者計画を成功させるためには、前任者の信念に共感し、同じ路線を続けていこうという気概をもつ人物を選ばなければならない。
第6部 WHYを発見する
アップルがイノベーションに成功してきたのは、カリフォルニア州パティーノ市(アップル本社がある市)にいるふたりの理想主義者が何年もまえに掲げた目的、理念、信条がいまも忘れられていないからだ。
スティーブ・ジョブズが「ぼくは宇宙に凹みをつくりたい」と言ったように、それはまさに競合他社がひしめく業界でアップルが続けていることだ。
ほかの人間と競争するとき、だれもあなたを助けたいとは思わない。
ところが、自分自身に戦いを挑むと、だれもがあなたを助けたいと思う。
私たちはつねにだれかと競争している。
ほかのだれかの上に立とうとする。よりよい品質。
より多くの特長。よりよいサービス。ようやって、つねに他人と自分を比べる。
すると、だれも私たちを助けたいと思わなくなる。
だが、日々、自分自身をよりよくするために出社したらどうなるだろう?
先週よりは今週のほうがよりよい仕事をすることを目標にしたら?
組織をよりよい状態にすることだけを目標にしたら?
もし、すべての組織がWHYから始めたらどうなるだろう?
決定はよりシンプルになるだろう。
忠誠心は篤くなるだろう。
信頼が共通意識になるだろう。
リーダーがWHYから始めることをたえず意識していれば、楽観主義が広がり、イノベーションが栄える。
 今月はこの本を選んだのは、TEDトークで動画再生2000万回 以上のロングセラーで、自社でも考え方を採用されているお客様に紹介して頂きました。
今月はこの本を選んだのは、TEDトークで動画再生2000万回 以上のロングセラーで、自社でも考え方を採用されているお客様に紹介して頂きました。
凄く印象的だったので、ゆっくり学びたいと思い本書を手に取りました。
映像で見た時よりも個人的には〈ゴールデン・サークル〉をより深く理解することができました。
また、著者の「リーダーは最後に食べなさい! ―最強チームをつくる絶対法則」も面白い本です。
お勧め度:★★★★☆ 星4つ
この書籍をAmazonで見る
(桐元 久佳)